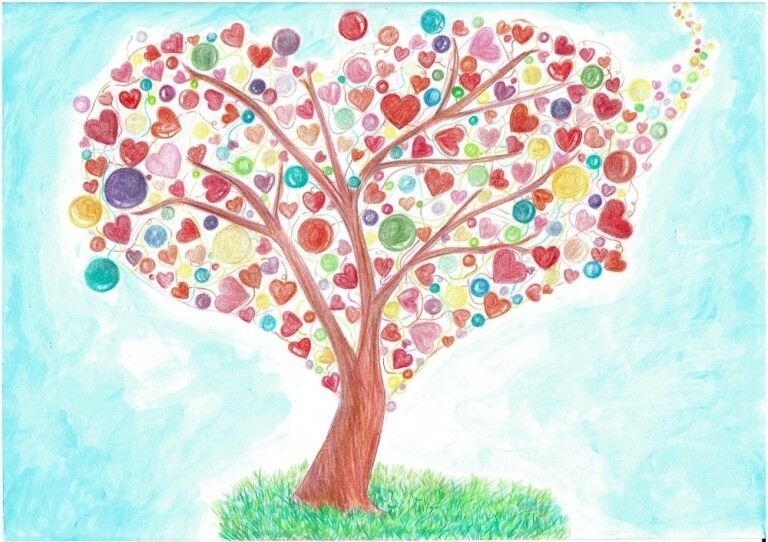子育て情報
子どもの発達に必要な事
私たちは、目を引くものについつい心奪われがちです。しかもそれが新しいものであればあるほど魅力的に見えてしまいます。小中学校の児童生徒たちにタブレット端末が配られ、(コロナ禍によることもありますが)プログラミング教育だ、新しい学びの形だと言われると、ついそういうものかと思ってしまうのも悪い癖です。人間の発達は、コンピューターにデータを打ち込んでいくように発達するわけではありません。
知識は大事だけど
最近は、乳幼児期の発達研究が進んでおり、様々な研究成果が発表されています。乳幼児期の教育保育のあり方がその後の発達にどのような影響を与えるかというものが多いのですが、5年、10年と追跡調査を行った結果、共通するのは、知識をたくさん詰め込むと、1年くらいはそうでない子どもたちよりも優位を保っているが、結局同じくらいに落ち着く、そうです。では、何がその後の人生の優劣に影響するのか、という研究はジョージ・ヘックマンの「幼児教育の経済学」に代表されるように非認知能力の育成です。
認知能力と非認知能力
「認知能力」とは、一般的には知能検査で測定できる能力のことを言い、「非認知能力」とは主に、意欲、自信、忍耐、自立、自制、協調、共感などの私たちの心の部分である能力のことを言います。
「認知能力」は目に見えやすく、そのため発達を計りやすいものです。言葉や数字など、その知識の量であったり、使いこなす能力など測りやすいものです。
「非認知能力」は、高い人は目標に向かって自己規律を持ち、困難な状況に対しても忍耐力を持って取り組む傾向があります。努力を継続し、挫折に屈しない姿勢を示すことができます。非認知能力が高い人は、他者とのコミュニケーションにおいても優れたスキルを持っています。相手の気持ちを推し測り、思いに添った対応が出来、良好な関係を気付くことができます。
もっと分かりやすく言うならば、非認知能力の高い人は、夢や目標を持ったなら、それに向かってそれを実現させるため日々努力を重ね、うまくゆかないことがあっても挫折することなく粘り強く考え一歩でも半歩でも近付こうとします。
また、その過程では仲間と協力し認め合い高め合いながら成功に近づいていく姿が想像されます。それゆえ、人生を成功に導くことができます。
「あなたは努力をすれば何でもできるのよ」「あきらめないでがんばれ」と言い続ければそのように導くことができるわけではありません。幼少期から、しっかりと自分と向き合って自己肯定感を育ててもらったことがその根底にあることがうかがえます。
人生の成功については、成功グループ群の学歴の高さ、所得の高さ、持ち家率の高さ、そして犯罪率や離婚率の低さがその裏付けとされています。人生観については人それぞれであり客観的に数値化することは大変難しいことです。ただ、今の自分の情況に満足し前向きに人生を歩んでいるかどうかという生きている姿で考えられれば良いですね。自分の周りの状況に不平不満を持ち、愚痴をこぼしているようでは、充実した人生を送っているとは費い難いですね。
急いては事を仕損じる
―早ければ良いというものではありません―
よそ様の子どもさんと比べて、歩くのが早かった、しゃべるのが早かった、3歳なのにもうひらがなが読める書けるなどということに一喜一憂しがちです。これらは親にとっては一つの安心材料であることは確かです。もちろん、これが良いということを否定はできません。
大事なことは、きちんと発達の道筋を通って来たかどうかということです。きちんと発達の道筋を通って来ての結果でしたら大いに喜び自慢してもよいことです。発達の道筋を通っていないと、本物の力が身についていない恐れがあります。
では、発達の道筋とは何かということを知らなければなりません。
言葉の習得
言葉を使ってコミュニケーションをとる力は、相手の意図を察する力に依存しています。まだ言葉を十分につかえない乳児の頃から、赤ちゃんに思いを伝えたり、赤ちゃんの思いを理解しようと接することで、原語によらないコミュニケーションの力が育ちます。おしゃべりをするようになっても丁寧に思いのやり取りをすることが大切です。たくさんの言語を知っているよりも、コミュニケーションの質(気持ちの伝え合い)を上げることが大切と思われます。
ウサギと亀では亀の勝ち
この寓話を知らない人は日本人にはいないと言えるほど有名なお話ですね。いくら力があっても怠けていてはいけない。力が劣っていてもこつこつと努力を重ねることが良い結果を生むということを伝える話と理解する人が多いと思います。もちろんそうだとも思いますが、あえて付け加えさせていただくと一足飛びにゴールには行けないんだよ、一歩一歩進んでいくことが大切なことだよということを教えてくれているようにも思えます。「千里の道も一歩から」という言葉もあります。一歩一歩踏みしめていくことが発達でも大切です。
学習でも基礎が大切だとよく言われます。言葉の習得も研究によると、教えたからしゃべれるようになったというのではなく、その前にアイコンタクトやスキンシップ、喃語等による気持ちの伝え合いがあり、それらが基となって言語による対話が可能となっています。目に見える発達の姿の裏には、目に見えにくい小さな発達の基礎がたくさんそれを支えています。
大切なものは目に見えない
「心で見なければものごとはよく見えない。大切なことは目に見えない」
(サン=テグジュベリ『星の王子様』)
目に見えるものを追いかけようとすることは仕方のないことです。でも、本当に大切なものは目に見えないことが多いものです。また、目に見るものに惑わされて大切なものを見失っていることもあります。一つ一つの出来事の意味をよく考えて対処しないと過ちを犯してしまう恐れもあります。子ども同士のいざこざを原因もよく確かめずに相手を責めて関係をかえって悪化させてしまう恐れも考えられます。また、我が子の話を鵜呑みにして誤解してしまうこともあります。もちろん子どもも嘘をつきたいと思っている訳ではありませんが、親から詰問されると自己弁護に走ってしまうことは仕方のないことです。どんな時でも私達大人が冷静に真実を見る目を養いたいものです。
「這えば立て立てば歩めの親心」と昔から言われているように、私たちは先へ先へと子どもの発達を望みがちです。まだ歩けないおさなごの手を持って歩かせる練習をさせたりもします。歩いてほしいという思いから歩く練習をさせればと考えてしまうのです。ところが、歩行の発達を詳しく調べてみますと二本足で立って歩く前に伝い歩きをしますね。二本足で立つバランスをとる力はその前の掴まり立ちをすることで身に付けられているのではないかと考えられます。
掴まり立ちをするための腕の力や体幹をしっかり保つ力はハイハイをたくさんすることで身についているようですし、ハイハイするための状態を持ち上げる腕の力はズリバイをすることで、というように、何か目に見える力を発揮する前に必ず準備段階が存在します。それは、先を見据えて考えたものではありません。
子どもが順を追って育っていくのは、順を追うことで発達に必要な力を身に付けていっているからです。いたずらに早く身に付けさせようとすると表面的な知識しか身に着かず、本質的なものごとの理解に行きつかなくなってしまう恐れがあります。理解に裏付けされた知識でなければ有効に使うことができません。一つ一つのものごとに丁寧に出会い向き合う経験が大切です。
子どもの「どうして」「なんで」「どうして」「なんで」に向き合う
子どもは身の回りのものや出来事は当たり前ですが初めてのものばかりです。好奇心が旺盛なので聞きたがります。「どうして」「なんで」「どうして」「なんで」、いちいち聞いてあげていると面倒くさくなってしまうのが本音です。しかし、そんな時がチャンスなのです。子どもが頭脳を開いて知識を取り込もうとしている瞬間です。こんな時こそ、子どもとしっかり向き合い伝えてあげると、乾いたスポンジが水を吸い込むように知識が吸い込まれていきます。欲しい時に欲しい物を与えることが一番有効です。逆に、十分水を含んでいるスポンジには、あるいはそれがラップで包まれていては(吸い込もうとしない状態)、いくら美味しいジュースを与えても吸い込ませることはできません。
興味関心を持てば伸びる
子どもも大人も興味関心のあることには積極的に取り組み、知識を得、理解を深めます。
考える力や知識を増やすためには興味関心のある活動に取り組ませることが大切であることはすぐ察しがつきます。問題は、大人が子供に興味関心を持ってもらいたいものと子どもが興味関心があるものとにズレがあることです。
頭の良い子は
何をもって頭が良いとするか考え方は様々ですが、ここでは一般的に学校のお勉強のようなものが得意な子どもについて考えてみましょう。人の話を、相手が何を伝えようとしているかを考えながら聞くことのできる子どもは総じて学校のお勉強はよくできます(当たり前ですね)。
本当に頭の良い子は自分で伸びます。おもしろそうだ、不思議だな、と思い自分で調べたり考えたりするから知識も増え理解力も高まります。偏った学力しかつかないと危惧する人もありますが、誰でも得手不得手はあるものです。全知全能の神でない人間は、協力することで、力を合わせて大きな力を発揮して社会を構成しています。
小さな頃から(興味関心のある)何事かに打ち込んだことのある子どもは、そののめり込み状況の楽しさを覚えていて、もっと楽しいかもしれない、何が出てくるのだろうとますますのめり込んでいきます。その過程で様々な知識を得、深く考えるので思考力も鍛えられます。
様々な物事に興味関心を持たせるために
いくら子どもに、何かに打ち込みなさいとか、興味関心を持ちなさいと言っても子どもの心は動きません。親が一緒に面白がったり、楽しんでやると俄然子どもも目の色を変えてきます。人が面白そうにやっていると、なんだろうとのぞき込みたくなりますし、一緒に楽しんでくれると楽しさも倍加され、ますますそのことが好きになっていきます。
周りで面白そうにしていると子どもは、すぐに興味を持って近づいてきます。
リビングで大人が雑誌を読んでいると、子どもは自分のお気に入りの絵本をもってきて隣で読んだり(見たり)します。
子どもの気持ちに関心を持ちましょう
子どもが何に興味関心を抱いているのかな、何をしたいと思っているのかな、子どもの思考を邪魔しない程度に探ってみるのも、子どもの心を理解するために役立つことと思います。(敵を知り己(おのれ)を知らば百戦危うからず)
体を動かせるのでなく心を動かせましょう
大人は、ついあるべき姿を押し付けたり、そうでないと嫌味を言って思い通りにさせようとすることがありますが、気持が動いていなければ行動も起きません。心が動いて体が動きます。大人の思いを伝え、子どもの思いにも耳を傾けじっくり向き合って理解し合うことが大切かと思います。(口は一つ耳は二つ)